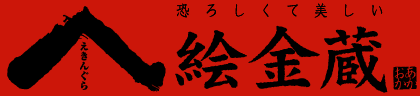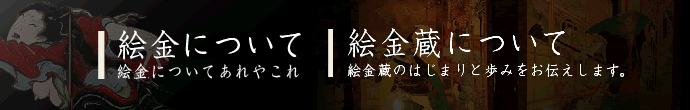絵金(1812~1876)とは

現在の絵金生家跡付近
そもそも絵金とは…
絵師・金蔵、略して絵金。江戸時代末期の文化9年10月1日、金蔵は髪結(床屋さん)の子として土佐藩城下の新市町(現在のはりまや町2丁目)に生まれました。
幼い頃より画才のあった金蔵は、江戸遊学などを経て、土佐藩家老桐間家の御用を勤める狩野派の絵師となり、林洞意と号して活躍しました。しかし訳あって城下追放となり、その後、町絵師「絵金」として親しまれながら絵を描き、二つ折りの大きな屏風に芝居絵を描く「芝居絵屏風」を大成させました。
この芝居絵屏風は、土佐の各地で絵金の弟子たちにより沢山描かれ、これらを描いた絵師も“絵金さん”と呼ばれたそうです。土佐ではついこの間まで子どもが絵を描いていると「絵金になるがや」、つまり「絵描きになるのか」という意味で使われ、絵金は画家の代名詞ともなっていました。
どうして赤岡に絵金蔵があるのか?
お城下追放となった絵金は各地を放浪した後、赤岡に住んでいたおばを頼って滞在していたとされています。そこで絵金は、町の旦那衆の求めに応じて、芝居絵屏風を数多く残しました。そのため、現在も香南市赤岡町には多くの作品が残っており、その作品を保存公開するための施設として、平成17年に設立されたのが絵金蔵です。その後の平成21年、赤岡の芝居絵屏風は高知県の保護有形文化財に指定されました。
なぜ、城下追放となり町絵師となったのか、絵金とはどのような人物だったのか…、答えは絵金蔵にてお確かめください。
絵金蔵、3つの使命
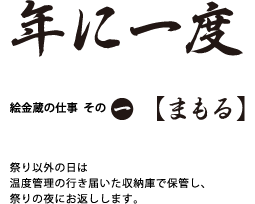
年に一度、夏の祭礼の暗闇に現れる
絵金の芝居絵屏風。
百数十年の昔に描かれたその芝居絵屏風は、
祭りの文化とともに生き、
今へと受け継がれてきました。
しかし、年月を重ね、
ずいぶんと傷みが見られるようになった今、
まちの人たちは考えました。
「絵金の芝居絵屏風を守りたい!
祭りの精神を失わぬまま…」
そして、生まれたのが「絵金蔵」です。
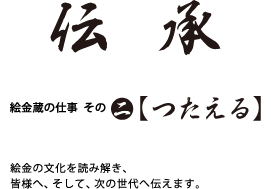
闇の中に蝋燭の灯りで浮かび上がる
極彩色の芝居の世界。
祭礼の夜を彩る絵金の強烈な赤“血赤”は、
邪気を払う魔除けの色として
庶民に受け入れられました。
そこには、当時の土俗信仰や
大衆文化との関わりがうかがえます。
絵金の文化が花開く瞬間、
そこには何があったのか。
当時の絵金観から見える文化があります。
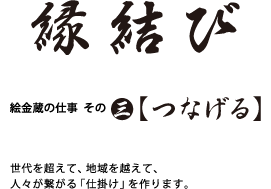
まちの人たちの
話し合いから生まれた絵金蔵には、
絵金を守るとともに、
「まちを元気にしたい」という思いが
たくさん詰まっています。
まちの人の憩いの場として、
新しい文化発信の場として、
「絵金蔵」から生まれる
新しい「縁」を紡ぐこと。
そして、次の世代へと繋げること。
絵金蔵は、そんな縁結びの
「場」でありたいと願います。